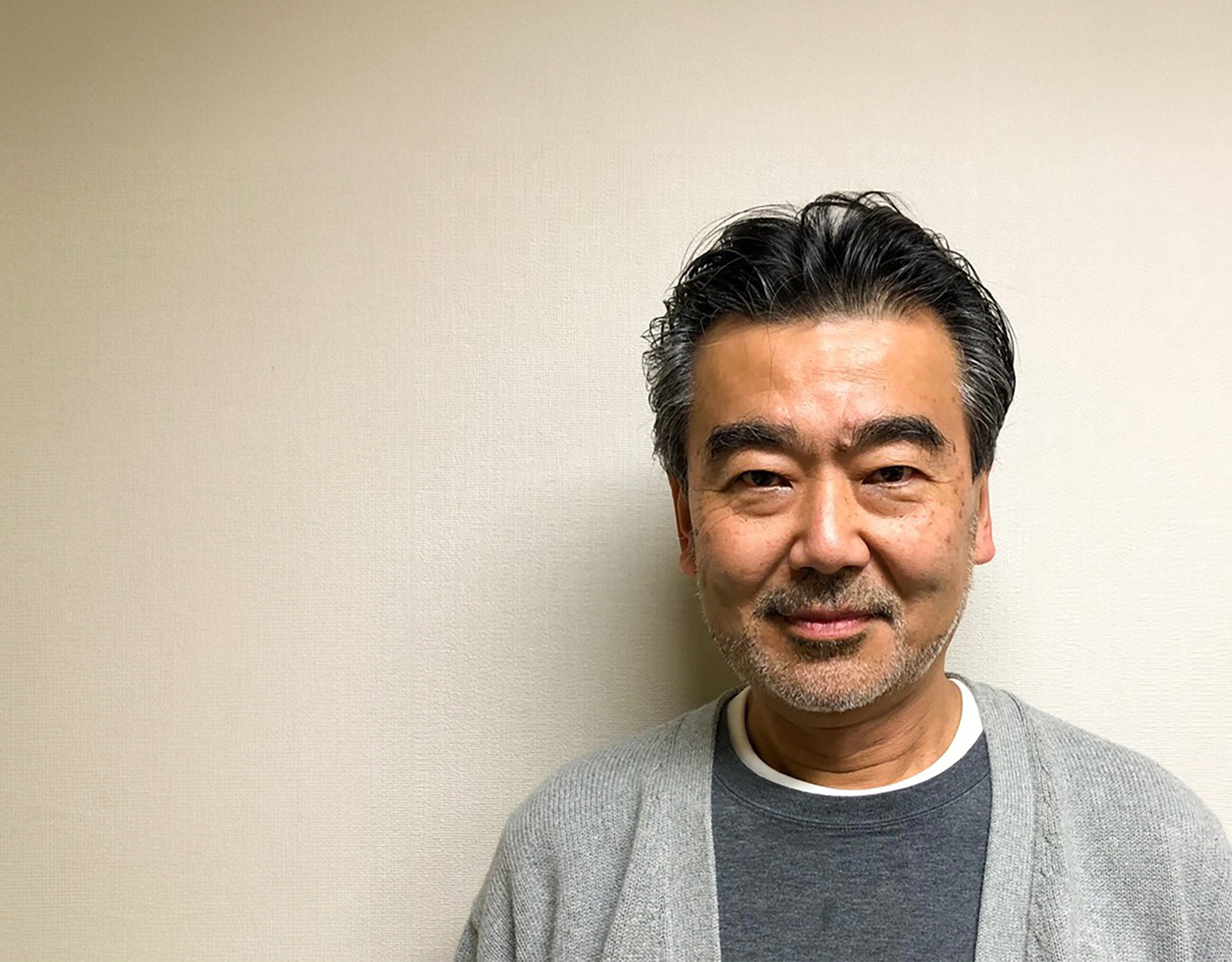
「住宅は生活のステージ」建築家・納谷学が大切にしているデザインや好きな空間について
個人住宅の設計を中心に、商業施設や店舗、集合住宅などこれまで200軒以上の作品を生み出している「納谷建築設計事務所」代表、建築家・納谷学さん。建築家としての活動の傍ら、関東学院大学や芝浦工業大学で講師としても活躍されています。今回は納谷さんに、大切にされているデザインやお好きな空間について伺いました。
建築家・納谷学

1961年 秋田県生まれ。1985年芝浦工業大学卒業後、黒川雅之建築設計事務所、野沢正光建築工房を経て、1989年に納谷学建築設計事務所を設立。2005年〜昭和女子大学 非常勤講師、2007年〜芝浦工業大学大学院 非常勤講師、2008年〜日本大学 非常勤講師、2016年〜関東学院大学 非常勤講師。主な受賞歴に2001年「ar +d 賞」、2008年「第2回JIA東北住宅大賞2006 大賞」、20011年「日本建築士会連合会 奨励賞」、2014年「JIA日本建築大賞2014 日本建築家協会優秀建築100選」、2020年「日本建築美術工芸協会AACA賞 優秀賞」2022年「グッドデザイン賞 ベスト100」など。
普遍的なものにユーモアを盛り込んだデザインを提案したい

まずは日常生活の中で大切にされているデザインについて伺いました。
「シンプルで使いやすい、飽きのこない普遍的なデザインをいつも考えています。機能的すぎるものはお堅くなってしまうので、そこの中にユーモアを感じさせる柔らかくて優しいデザインを提案できればと意識しています。」

これまで手掛けられた作品は白が特徴的な印象ですが、そこもシンプルということを意識されているのでしょうか。
「生活していくとものが溢れて、同時に色も増えていくので、住宅自体は主張しないようにしています。あくまでも住宅は生活のためのステージ、舞台だと考えています。」
300個のサボテンを愛でられる温室がお気に入り

建築家として、お好きな空間はどういったものなのでしょうか。

「自邸がちょっと特殊で、6階建なんです。庭がないものですから屋上が唯一外とのつながりを持てる場所で、空が見えて気持ちが良いので気に入っているスペースです。僕はサボテンが趣味なので、屋上に温室を設けて、300個くらいのサボテンを育てています。こっそりと上に上がって、それらを愛でる時間を楽しんでいます。」
土木より短期間で結果が出るのが建築だった
どのような経緯で建築家を目指すようになったのでしょうか。
「元々は土木に興味がありました。そこで高校生の時に進路を決めるにあたって、土木のことを調べたら、一つの仕事が完了するまでに結構時間がかかると気づいたんです。そこで、もう少し短期間で結果が出るものがいいなと考え直して、次に大きいものが建築だったんです。」
実際に建築家になられて、土木ではなくこちら側でよかった、と思う瞬間はありますか。
「公共建築であればお客さんが喜んでたり、使う人が喜んでたりする光景が見れますし、住宅であればクライアントと直接会話して、希望を叶えた時に最高の喜びになりますね。」
建築とプロダクトを両方経験できた

納谷さんは芝浦工業大学を卒業された後、黒川雅之さんの建築事務所に入所されましたが、そちらではどのようなことを学ばれましたか。
「僕が入所した当初はちょっと特殊で、建築に加えてプロダクトデザインをやり始めたタイミングでした。建築の担当スタッフが6人、プロダクトの担当スタッフが4人くらいで半々くらい。両方の仕事を小さいものから大きいものまで見れたのが大きな経験でした。実際そこでの経験もあって、最近『LAMINA(ラミナ)』という家具のシリーズを立ち上げて、全国で販売しています。」
自分が手掛けたプロダクトが並ぶことで空間の完成度が増す

建築家の方でプロダクトまでご自身で作られる方は多いと思うのですが、相通ずるものはどういった点でしょうか。
「黒川さんは当時から『灰皿も建築だ』と仰っていました。自分が作った住空間なり空間に自分の感覚で作られたプロダクトがあることで、より空間の完成度が増す、ということですね。」
それぞれの建築にはローカリティがある

納谷さんは秋田県能代市の出身ということですが、秋田の風土が設計に影響を与えたポイントはありますか。
「実際に秋田での設計にあたっては、当然冬のことを意識して断熱を重視して計画を進めるのですが、それは秋田だけではなく、沖縄には沖縄の生活の仕方があるし、風土があるのと同じように、空間づくりはそれぞれの地方のローカリティとつながるデザインになるのかなと感じています。」
住宅はステージとして、主張のないものにしたい
あくまで空間はステージであり、主張しない普遍的なデザインを目指していると語る納谷さん。そこに住まう人々の暮らしを考えた、将来を見据えた視点によって、普遍的に愛される空間は生み出されるのかもしれません。